どの子も、いじめの被害者にも加害者にもなり得る

子どもの自死が多いのは、夏休みの後半から休み明けにかけて。その中には、いじめを苦にしての自死も少なくない。いじめ事件が報道されるようになって久しいが、現代の社会はまだこの問題を解決できていない。『いじめで死なせない 子どもの命を救う大人の気づきと言葉』(新潮社)は、20年以上にわたって記者・キャスターとしていじめ問題を取材してきた日本テレビの岸田雪子さんの一冊。岸田さんが取材現場からすくい上げてきた被害者やその家族の言葉から、大人が子どもとどう向き合うべきなのかを考えさせられる。どの子どもも、いじめの被害者にも加害者にもなる可能性があることを知ってほしいと、岸田さんは言う。
1970年東京都生まれ。早稲田大学法学部を卒業、東京大学大学院情報学環教育部修了後、日本テレビに入社。報道局社会部文部省(現・文部科学省)担当記者、政治部自民党担当記者を務めた後、ディレクターとして「真相報道バンキシャ!」「NEWS ZERO」の立ち上げに関わる。2004年より報道キャスターとして「ズームイン!! SUPER」「ザ!情報ツウ」「スッキリ!!」「DON!」などのニュースコーナーを担当、BS日テレ「深層NEWS」のメインキャスターも務める。「情報ライブ ミヤネ屋」で宮根誠司氏との軽妙な掛け合いが話題となった。2017年からは報道局解説委員として、再び文科省記者クラブを担当。育児中の日本テレビ社員らで作る子育て支援プロジェクト「ママモコモ」でも活動している。
「いじめの認知件数は多くていい」
――岸田さんはこれまで20年以上、いじめ問題を取材されています。20年前と比べて変わったことはありますか。
岸田:相談の体制づくりはある程度は進んできていると思います。20年前はそもそも電話相談窓口が、「いのちの電話」のようなものしかありませんでした。子どものための「チャイルドライン」が全国に普及し、今はLINEなどSNSでの相談体制もあります。あとは、政府が「いじめをどんどん見つけて」「いじめの認知件数は多くていい」という意識を持つようになったことが変化だと思います。
――「いじめを減らせ」では、問題が表面に出てこなくなるだけだから「見つけろ」と。
岸田:はい。ただ、それが現場で浸透しているとは言えません。政府がそのような姿勢を取ることはもちろん重要ですが、日々子どもたちのトラブルと接する教師や教育委員会には、まだ「いじめがあると学校の評価が下がる」と考え、いじめを見て見ぬふりをしてしまうことも多いのです。変わってきている学校も増えてきていますが、変わっていない学校もあります。
――変わる学校と変わらない学校の違いは何でしょうか。
岸田:取り組もうとする校長先生がいるかどうかが一番大きいと思います。なおかつ、先生同士で情報を共有するチームワークを作れているか。担任の先生1人だけでいじめを把握し、対処するというのは無理があります。
教師へのサポートが子どものサポートになる
――複数の目が必要?
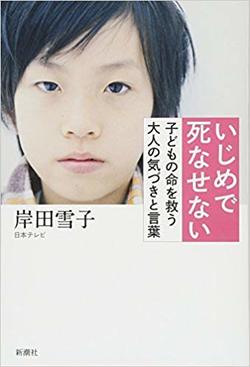
岸田:いじめの被害者と加害者が全然違う話をすることも多いわけですよね。そのときに教師が1人だけで解決しようとすると、判断が偏る場合もあり、危険です。複数の大人が見守り、「そういえばあのときも一人でいた」とか「不自然だった」といった情報を共有して問題を把握する必要があります。
――90年代頃はまだ、「いじめられる子にも問題がある」という雰囲気が強かったように思います。その状況は変わってきていますか?
岸田:変わっているところもありますが、まだまだ残っていると思います。そうでなければこんなに簡単にいじめが起こることはないのではないでしょうか。大人がそういう価値観をまだ持っていて、子どもたちに伝わってしまっている面もあると思います。「いじめられる子は弱い子」「言い返したり殴り返したりできないのは弱いから。強くなれよ」って論理を。それは違うよ、人を傷つけてはいけないよねということを真剣に伝えないといけません。
――学校の中にも努力している先生はいると思います。一方で、『いじめで死なせない』の中で挙げられている教師の対応の中には、これはちょっとひどいなあ……と感じるものも。
岸田:学校の先生って、基本的に子どもが好きで夢を持って教師になってらっしゃるので、特に若い先生方は、いじめで子どもたちがこんなにお互いを傷つけ合う事実を目の前にして、まずびっくりしてしまう。加害者は「あっちが悪い」、親も「うちの子がいじめたという証拠はあるんですか?」と言ってきて、どうしたらいいかわからなくなるということがあると思うんですね。
――だからこそ、先程仰ったように、複数体制が必要なのですね。
岸田:はい。そして親は、そういう現実を知っておくことが必要だと思います。適切に対処してくれる先生もいるけれど、お預けしておけば大丈夫というわけでもない。先生が忙しいからこそ、子どもの状況を共有して、先生をサポートする。先生のサポートは子どものサポートにつながるので、学校に親も含めた第三者の目が入ることは大切です。
反省のない加害者、体罰を容認するその親
――本書の中に、2011年に起きた滋賀県大津市の男子中学生のいじめ自殺事件について、加害者側に損害賠償を求める裁判の傍聴に行かれた際の記述があります。加害者の少年の証言には反省の気持ちが感じられないことが衝撃でした。
岸田:裁判ですから否認するだろうとは予測していましたが、私もショックでした。平然と「いじめではない」と。「りんごは赤い」と言うのと同じぐらいの当たり前のような口ぶりでした。
――あれだけ大きく報道されましたし、当然後悔や反省はあるのだと思っていました。
岸田:なぜなのだろうと思いますが、逆に言うとそうでなければあそこまでのいじめはできなかったのかもしれないと思います。その後、加害者の親の言葉を聞いて腑に落ちるところがありました。
――加害者の親は息子に対して「痛みを味わってほしいから」という理由で、「本当はたたきたくないが」手を上げたことがあったと。岸田さんは、「暴力は連鎖する。『理由』をつければ暴力をふるってもよいのだ、と身体で覚えた子どもは暴力というものに対するハードルが低くなる」と書かれています。
岸田:体罰を容認する意識は社会に根強くあります。その理屈が正論のように聞こえてしまうことについて、「おかしい」と伝えていかなければいけないと思います。
いじめの有無ではなく、いじめへの取り組みの評価を
――いじめ事件が報道されると、いじめを許すなという世論は高まります。しかしその世論がストレートに良い方向へ向かわないのがもどかしいと感じます。
岸田:難しいですよね。法律を作ればそれだけで変わるものでもありません。教育は地方自治、もっといえば学校自治です。「心身に苦痛を与えれば、いじめ」と被害者の視点から定義したいじめ防止対策推進法自体は進んでいると思いますが、学校現場にはその理念がなかなか浸透していない。社会の意識を変えていくこと。そのために、被害側の実態をあらゆる大人が知ることが必要だと思っています。
学校の評価は生徒の学力で図られがちです。もしくは、いじめがあるかないかで。でも本当は、いじめがあったときにどのような取り組みを行い、解決するか。学校側はそれをアピールしないといけないし、地域の大人たちはその取り組みこそを評価していく。その発想の転換、意識改革が必要だと思います。
――学校のHPなどにいじめ対策は書いてあるのでしょうか。
岸田:いじめ防止対策推進法では、基本方針として学校ごとにいじめ対策を決定しなければならないと義務付けられています。ですから学校のHPには「我が校の取り組み」が書いてある。けれど、たとえば「早期発見に努める」という方針について、どんな取り組みを具体的に行っているのか。絵に描いた餅ではなく、実行されていなければなりません。先生も親も、お互いに遠慮しがちなところもあるのでコミュニケーションを取って。風通しを良くしていくことが、結果的に子どもを救うのではないでしょうか。
自分の子どもが加害者だと気づいたときは
――親が、自分の子どもがいじめの加害者だと気づいたときは、どのように対処すれば良いのでしょうか。
岸田:まず、被害者にも加害者にも誰でもなるものだと思っていてもらいたいです。誰も無関係ではありません。一番難しいのは、加害者本人がやむを得ずいじめに加わり、罪悪感を持っているときの対応です。たとえば、主導的役割の子どもから「無視しないとお前もいじめる」と言われていじめに加わったような場合や、被害を受ける側だったことがあるような場合。
頭ごなしに「ダメだ」と言ってしまうと、元から傷ついている彼らは家にも居場所がなくなってしまいます。話を聞いて、いじめの加害から抜けられる方法を一緒に考えてあげることが大切です。
もちろん、はっきりと「ダメだ」と言わなければいけない場合もあります。たとえば、被害者の裸の画像をSNSにアップしたりしているのであれば、「それは犯罪」と教えなければいけません。その上で、「どうしてそんなことをしたの」と、加害行為の背景にある、子どもの心の奥にあるものを、聴き出してあげてほしいと思います。
加害者でも被害者でもない、傍観者の子どもが鍵
――海外のいじめ対策について、良い取り組みだと思うものについて教えてください。
岸田:本の中でも紹介していますが、ノルウェーの心理学者ダン・オルヴェウス氏の「いじめ防止プログラム」。20年前に取材して、日本でもいろいろな学校に導入されるだろうと思っていたら、あまりまだ知られていないのでもう一回伝えたいと思って書きました。
1、私たちは、他の人をいじめません。
2、私たちは、いじめられている人を助けます。
3、私たちは、一人ぼっちの人を仲間に入れます。
4、私たちは、もし誰かがいじめられていれば、それを学校の大人や家の大人に話します。
その上で、スローガンだけで終わらせないために、子どもたちは定期的に話し合いを行うなどの取り組みを勧めている。
岸田:この方針のいいと思うところは、いじめを見ている周りの子どもたちにも呼びかけていること。「いじめは悪いことだよ、やめよう」だけではなくて、「友だちを助けることは命を守るために必要」「友だちがいじめられていたら、大人に言いましょう。それは当たり前」と教えている。いじめに気付いている周囲の子どもたちに働きかけることは、いじめ対策のカギになると思います。
――確かに、いじめを知っているけれど、どうすればいいかわからないという子どもも多いと思います。
岸田:被害者と加害者だけの問題にしてしまうと解決が難しいけれど、周りで声を上げられない子どももたくさんいて、その子たちも何もできないって自分を責めて苦しんでいる。その子たちの声を聞くことを当たり前にして、大人との信頼関係を作る。それが大事だと思います。日本では、その部分が遅れているかもしれません。
・どの子もいじめの加害者にも被害者にもなる可能性がある
・親と教師がコミュニケーションを取ることが子どもを救う
・学校のいじめへの取り組みについて、評価する目を持つ